〔十七〕
漸 (よう)やくに 涅槃(ねはん)の国の 一の宮
人の情けも 甘き酒杯に
ようやくアスファルト道に出たのも束の間、吉田跡というバス停に、しるべの石像があるので横道へと進み行く。しばらく行くと、進入不可の立て札があり、多少ためらいつつも旧ヘンロ道だから良かろうと進み行く。例の岡山の人達のしるべ札も二、三あった。ただし各所で見かけたのよりは小さく古めかしく、字も読みにくかったので最近のものではなかったのに気付けば良かったのだが、まあ足を踏み込んだ勢いで進み行く。
小雨摸様の山中でわびしく、小さな毘沙門堂に出る。滝があったりしてまことに幽すいというよりは、寒々とした趣きの処であった。ここまではまだ良かったのだが、それからの山道で草深く道に迷う。さらにリュックの右ヒモが切れ、雨も少し酷(ひど)くなり、リュックのヒモを結ぶ余裕もなく、五輪塔かしら三基見付けたので、道もあるだろうと精出して進み行くと、段々と道らしきものが消えてしまい、こんどは前の石塔よりは少し小さ目のが十ばかり、おそらくは昔の古い行者さんらの墓所であろう、ヤブの中に転がっている。心中おだやかならず、ひたすら一歩一歩とヤブこぎしつつ進む。
お寺の白壁が見えた時のホッとした気分はなんともいえないものであった。全身びしょ濡れで納経所にたどり着いたのが十二時四十分。本堂諸堂御陵と一巡りする。
宿坊は不可とのことなので、近くの簡易保養センターに宿をとることにする。早い宿取りではあったが、風呂に入り、洗い物や繕い物をかたづけて、広島にも電話してくつろいだものである。
七月二日、火曜日。六時過ぎ起床。荷づくりをして朝風呂に入り、朝食を済ませて出発は八時半。十時四十五分には八十二番根香寺(ねごろじ)に着く。先日よく晴れた日に車で参った時には眺めもすばらしかったが、この時分には霧が出ており、一人ボツボツと歩いたものである。
十二時四十分、鬼無町。これより円座まで、しるべ石や小祠などをたよりに、又、人にたづねつつヘンロ道とおぼしき道を行く。雨降り激しく、多少の難儀はしたものの前日のヤブコギとは違って、平地の道は心軽く歩いたものである。
一宮寺手前の食料品店でトマトやパンを買うつもりが、店の人に接待して貰う。讃岐弁かしら、とっつきにくい口調(くちょう)の奥さんではあったが、有り難いことであった。
十四時半、一宮寺に入る。雨が降っていたのだがお参りの人繁く、堂内にも多くの人々が上がって休息などをしておられた。隣りの讃岐一の宮(田村神社)の輪越(わごせ)の祭りとて、多くの人のお参りであった。
高松より二里の道を歩いて来たという、八十四歳のおばあさんが色々と小生の宿のことなどを心配されたことである。二度三度ならず、五度六度と九度九度しく大師堂にとまれなければ、小堂なれど稲荷堂があるから云々と、ひたすらに小生の宿の心配をして下さったものである。また、連れのお年寄りからも遍路の経験話を種々伺った。
さてこのおばあさん、帰り際(ぎわ)にも琴電で屋島の下まで一緒に行かぬかなどと、なおも小生の宿の心配をされるので、流石(さすが)に連れのお年寄りも苦笑しておられた。
いづれにしろ縁日とはいうものの、多勢の人々のお参りがあり、堂内に上がって大数珠をとって肩などにお加持しているのも珍しいことであった。
さて、お寺にて可成りの人に接待していただき、隣りのお宮にゆくと甘酒の接待があった。小生好物のことなれば、たちまちに数杯も飲み干す。その際、持って行きなさいと四合ビン一杯に詰めていただく。
一休みして、お接待の手伝いをしておられる人々と色々話をしている内に、Nさん宅に善根宿を頂くことのなる。先程のおばあさんの気持ちもここにやっと成就したのである。
白峰寺への道で色々難儀したことによって、本日この一の宮のお参りに具合よく行き逢ったことは、大師のはからい神の導きと申すべきか。
来し方に、種々様々な”もしかしたら”という、クレオパトラの鼻がもう一センチメートル低かったら歴史は変わっていただろう、と言うようなことを思うことがあったが、具体的な現実の出会いは己れの計算出来ぬ大師のはからいであれば、歩くほどに身に沁(し)みてくるものである。
母のぶんも 一つくぐる 茅の輪哉 一茶
我知らず 神のはからう 道なれば
大師と共に 茅の輪くぐる
〔十八〕
八十八(やそはち)の 寺を結びて 玉磨く
遍路の道に 跡を残して
七月三日、水曜日。N家にて朝食を済ませ、バスに乗って一の宮まで行き、ふたたび歩き始める。時に八時五十分。昨日宿の心配された老婆の連れの人に教わった、詰田川近くの小堂には十一時に着く。そこで早目の昼食をとることにする。近在の人がお茶を接待して下さる。
さて屋島での登り道は、日がカンカンと照って、雨中よりも又違った苦しき道であった。十三時十五分、八十四番屋島寺に着く。納経所の老人、どうしたものか押印のページを間違える。獅子ヶ嶽より瀬戸内海を眺め、十三時五十分に八栗寺に向かう。
寺の山門を出たところで財布を見つける。二百数十円と印鑑(大熊姓)と鍵が入っていたので、中途駐在所に届ける。丁度屋島はそこの所轄(しょかつ)との由。若奥さんにジュースを接待していただく。
八十五番八栗寺への登山路は案外に短くて、寺には十六時に着く。納経を済ませて次の八十六番志度寺には十七時四十五分着。諸堂が多くあり、五重の塔を建設中であった。
寺では宿を取れず、志度駅の待合室に泊まる心づもりで、近くの喫茶店でカレーを食べ、日記の整理をする。なおそこに荷物をあずけて風呂屋にも行く。ここの奥さんの父親は、毎朝志度寺に行き、朝の鐘を撞いているとのことであった。
駅待合室は泊まりはいけないとのことで、外のベンチにて眠る。
七月四日、木曜。四時半起床。五時発。八十七番長尾寺には六時半に着く。二、三人老人の方が境内を掃除しておられた。七時過ぎに納経所に行くと、納経料は接待しますとのことであった。
いよいよ最後の八十八番大窪寺に向かう。七時半に長尾寺を出発、五時間ばかり歩いて十二時半着。最後となれば、なんとはなしに足軽くはあれども、歩みがのろくなったのは致し方あるまい。寺に着く前に大キジを打ったので、気分身体共にスッカリとして山門を登り行く。納経を済ませて記念の写真を撮(と)り、門前の店でうどんや甘酒をいただく。
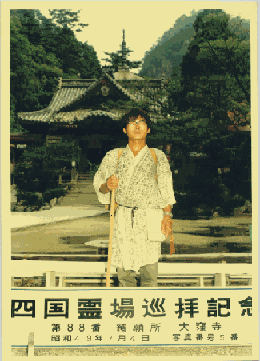
徒歩遍路成就
遂に八十八ヶ所を歩き終える。まずは一大安心。これから高野山奥の院へと向かう。列車や船の便の時刻とにらみ合わせ、少しばかり歩いて、バスを利用して徳島の方へ出ようと歩きはじめると、たちまちに雷鳴激雨。タオルはどこかに忘れたものか見失っており、白衣の紐も落としていたのを少しあと返って拾い戻し、あたふたと心中おだやかでなかったが、これはどうでも一番まで歩き通さん、最後の徒歩行ならんとて、心をしかと定めて歩く。
そうこうして十九時には、十番切幡寺前の宿に入る。全身びしょぬれですぐに風呂に入る。この日志度から当地まで十里余りは歩いたであろう。
七月五日、金曜日。六時半起床。朝食前に切幡寺へ参り、宿出立は八時十五分。これより七番、六番、五番、羅漢寺、三番、二番と、道端の寺にお参りして、十五時に一番霊山寺に着く。ここで漸く八十八の寺を、徒歩で巡って円環を結ぶこととなった。一の宮の茅の輪くぐりが思い出される。
一番納経所で満願の印を押してもらい、高野山までの交通の便をたずねて板東駅に向かう途中から駅までタクシーの接待があった。それから徳島へ、さらには徳島港へ。フェリーで深日(ふけ)港へ、そこからすぐに電車の便があり、みさき公園で乗り換え南海和歌山駅へ行く。三十分の待ちで橋本行きに乗る。橋本駅に着いたのは十九時半である。すでに高野迄の便がなく、駅待合室に泊まる。
七月六日、土曜日。四時半起床。五時八分高野行きに乗って高野山には六時に着く。ただちに奥の院に参り、お礼の宝号を唱え、初めての高野参りでゆっくりもしたかったのだが、すぐに山を下り、京都へ向かう。友人の米丸君と待ち合わせである。苗字の米の字が、八十八に分解できるのも面白いことである。
それから二、三日京都で過ごし、十日早朝に広島に帰る。
ここまでは 人生航路の 小手調べ
これから歩む 新米(しんまい)大師
…一応遍路は終わり、次には現在地に辿 (たど)り着く話…
〔十九〕
独り行く 心の所在(ありか)求めつつ 雲の行方(ゆくえ)に 水と流れて
君も行き 行きつく果ての 道の辺に 野菊は笑みて 待ちてありしか
ヒト独り 行きてなお行く 辺路行 青き鳥満つ 心次第で
時経れば 曇り晴れ行く 道の辺に 心注ぎて 確かな華を
以上四首の歌は、高校の後輩のY君が四国行脚 (あんぎゃ)の途次小生の処に立寄った時分(昭和53年11月21日来堂。23日早朝出立)にものした歌である。