〔九〕
狭く急な坂道を下り、小さな橋を渡り、灯りめざして田んぼの中を少しゆくと、農家と思いしも、かなり大きなお堂の前に出る。石段を上がり、庫裏の方に声をかけると老婆が出てこられ、快く招き入れてもらう。
ゆらぐ灯(ひ)に 迷うて入りし 道ならず
高野の谷に 今に大師が
この寺(堂)は、今大師と称す。明治になってからか、一人の回国行者(名を喜伝坊、六根祈念行者大菩薩と号す)が、種々の法力をみせてこの地に眠るという。当時、現在のバス道は無かったのだが、やがて牛馬(つまり車のこと)が上の方を〜つまり昔は、遍路道が谷に在り、今の道が山腹にあるので〜通るようになると予言していたとのことだ。堂の施主は、津倉淵在住の植田氏にて代々の供養祭りごと怠りなくつとめておられる。旧暦の九日と二十一日に、その前後三日間通夜篭もりされ、当日には相当の遠方からも多数の人がお参りされているようだ。
(*現在はこの寺のすぐ側を新道が通りトンネルが抜かれている)
伊豆田峠をはさんで一里半の所には市ノ瀬の大師堂が元禄(*天和)年間の建立で有名であるが、一方こちらの今大師も近代に成立したお堂として今も語り継がれていることも多く、もっと詳しく紹介できればよいのだが、今のところたいした資料も持ち合わせず残念なことである。
さて、その夜行者さんらと色々と話しにはずみ、みんなで勤行すませ床についたのは一時頃であった。
小生と今一人、前夜よりとまりたる老遍路あり。尾道出身、大阪在の人とて、納経帳も満足にもちおらず、多少芝居がかって「天の神が云々」と話しだしたるは噴飯ものであった。この人とは、後日伊予の国分寺にても出会う。また数ヶ月後自転車にて国道(十一号線)をこぎゆくのも見かけたが、今頃は何処に思案の雲の下か。
六月十二日水曜日、六時起床。洗顔に下の流れに降りれば、行者さんらは日拝等をしておられた。
朝食すませ、十時頃には老遍路は追いたてられるが如く旅立ちたるも、小生はゆっくりとかまえ、出立したるは十四時半頃である。特に名残惜しみたる老婆あり、<帆陰いくの>なる人にて以後何度も手紙交わしたるなり。七十九才(昭和五十六年現在にて八十五・六才)にて体は小さくもなかなか口達者にて五体満足で、昨年(昭和五十二年のこと。なお昭和五十五年十月にも足摺に行く中途に立ち寄りて再会を祝す)南予にゆきたる便に、中村市にこのおばさんをたずねたるに、丁度在宅にて共に再会を喜んだものである。
小生独行中、一番なつかしきはこの老婆なり。若い時分は娘遍路とて三人連れかで三ヶ月くらいかけて呑気(のんき)にお四国めぐりをされた由。
独り行く 我に老婆の まごころで
今に大師が 道を守りて
さて峠を越して下の加江川を渡り、海岸沿いに出る。しばらく行くと久百々(くもも)という所があり、うしろからきた遍路バスが停止して中に乗っておられる人々、口々に小生の同乗を勧(すすめ)められたり。
有り難きことなれど折角歩いてつながんとしたる道なので、ご好意を辞退する。ただ、おもしろきことあるは、後日今治駅裏の泰山寺への道すがら、自転車にてうしろよりきた若い女の人が小生に声をかけられ、少し話しをするに、この久百々にて停止したるバスに乗っていたとのことであった。
今大師にて飯盒(はんごう)一杯のゴハンに米一升、それに間食用の菓子などをいただき多少リュックが重くなりたるも、心とともに足取りも軽やかであった。
大岐の浜を眺めつつ行くに、坂道をブレーキをきしませて下り来る自転車あり。岡林という姓の人なるが、山桃がありますからとて、小夏みかん十個ばかりと接待していただくなり。おそらくは家の子供へのおみやげものであったのだろうが、いただくなり。山桃は小粒の初めて食すものなれどなかなかの珍味であった。
今少し歩きて以布利(いぶり)という町の民宿に宿取りたるは、十九時三十分頃なり。ここらも大体に釣り客相手の宿らしく、素泊り千五百円なれど、一風呂浴びて飯盒のゴハンを食べおるに、おかず四品も接待して頂く。
〔十〕
幾筋も 助けの御手(みて)を のべて待つ
八十八(やそはち)の 道に大師を
六月十三日木曜日。五時半起床。昨夜お茶をたっぷりと飲んだせいか、夜半発汗ひどく、目覚めた時分には体がベトベトであった。
足摺から伊予への道は、山の中がよかろうと三原村のコースをゆく算段なれば、荷物は宿にあずけ、わずかな小物もちて三十八番金剛福寺にむかう。室戸辺の海岸とは違って人家も多く、風景もスッキリとしていなかった様に思う。ただ四国も西南端となれば室戸辺とは樹相もかわり、亜熱帯性植物群落の好資料とあれば、その道の学者には貴重なものであろう。
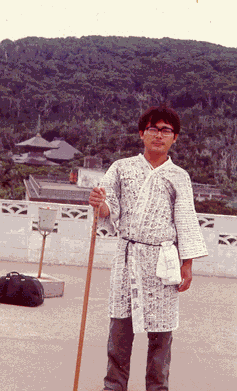
昭和49年6月13日木曜日、筆者26歳 衣に注目!
納経すまし、展望台に遊ぶ。倉敷の人にて有馬嘉一君、単車にて四国一周の途にて、ここで小生一コマほど写真撮影してもらい、後日家の方に送っていただく。お寺やその後方の風に押しなびかされた樹林を背景に写したものである。
さて帰りは少し急ぎて、宿には十三時五十分につき、十四時半に出立。久百々、下の加江河口へとってかへして、三原村に入る。
この下の加江川辺にて下校の中学生とおぼしき自転車の男の子「さようなら」と声をかける。これは実に心地良きものであった。先日も、四万十河口をすぎたあたりで、かわいらしき小学生の女の子、「さようなら」と声をかけて行く。リンゴの如き紅さしたるほほに、下向きてはにかみながらのことである。また室戸海岸に出るまでの山村にてもかかることあり。接待とはちがった格別のめぐみである。
しかし、この中学生と出会いて少しゆくと、路辺の家の老婆、孫にいうに「グズグズいうと、ホレ、こわいおじさんにつれていってもらうよ」云々。これは前にも一度ききたることである。子供をあやす方便なれど、こちらの耳にきこゆる時は、はなはだ不快なことだ。
山道にかかりて雨もふりはじめ、十九時大河内神社と言う所に宿借りる。多少は荒れているが、雨をしのげれば幸い。空き地に、ブランコやその他の遊具が、赤青などハデなペンキを塗ったのが、雨にけぶりてあるのがなんとなくわびしく、ランタンともしコーヒーを沸(わ)かし、独りですする。
この神社に泊まるには、一応土地の人承諾いただく。ただし何処にてもいわれることなれば、煮炊(にた)きすることは遠慮する。往時ヘンロの不始末により、火災起こしたるも少なからずあったものであろう。昨日は、千五百円(宿代、牛乳キャンディ代)、今日は、牛乳百円パン七十円キャンディ三十円、計二百円の出費である(納経賃は別)。
六月十四日、金曜日。五時十五分、起床。四十五分発。栗栖野(くずの)八時二十五分。柚の木、梅の木とすぎて十時二十分川原におりて飯盒をたく。この遍路中初めてのことである。所持していた玄米餅やきて食したこともあるも、ゴハン炊(た)きたるは初めてのことだ。一休みして十二時十分発。
国道五十六号線に出ると、一老婆親しく話し掛けてき、以前泊めたヘンロの話などする内に、この近所に知り合いの家あるとて、そちらに招きてお茶の接待。そうこうして三十九番 延光寺につきたるは二時五十分であった。
如何程(いかほど)の 修行為してぞ 独り行く
菩提(ぼだい)の道に 足取り軽く
ようやく土佐の札所を打ち終えて、伊予の国へと打ち進む。延光寺三時三十分発。県境目指し心急ぐ。宇和島市に十五日中に入りこまん意気込みなれば、結局観自在寺門前(御荘町平城)まで歩く。今にしてみれば随分と歩きたものと驚きおる。手頃な宿もみつからず、深夜なれば寺の縁にでも寝転ばん心づもり。
県境の橋越したるは十八時四十分。そこの停留所前の店にてお茶を出してもらい、飯盒のメシを食しサイダーを飲みトマトをよばれ、十九時出発。八時頃暗くなりたる田んぼに耕運機の音などしおれば、小生もまだまだ歩くべしとて心励まされたものである。
さて十時近く城辺のにぎやかな街中を歩き抜け、御荘町に入りて少し行くと、風呂帰りの若い人おれば観自在寺への道のりをたずねるに、もうすぐなりとぞ。一緒に話しもってゆくに、門前の下宿屋にいるからとて善根宿いただくことになる。県土木課の職員だそうで、実家は今治泰山寺のすぐ下とのこと。今頃は何処の事務所に座っておられることやら。この人(名は加藤勇君、昭和五十六年現在二十八歳位)のいる下宿屋は、元々ヘンロ宿だった由。猫をたくさん飼っていたように思う。
此度(このたび)も 見えぬ大師の 綱と綱
ここに結びて 不思議な巡り